2014年12月17日(木)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、高幡童子、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
今年最後の例会は皆さん定刻前に集合され、意気込みの高さを感じました。いつもながらの多彩なテーマと内容でしたが、グーグルのPICASAというツールで何気なくクラウドに上げたスナップ写真が、いつの間にか先方で画像解析されていたという話は実に不気味でした。また、世に出回っているサプリメント製法やジェネリック薬品の実態など恐ろしい話も興味深いものでした。
なお、会で話題に出た新建材は「CLT(Cross Laminated Timber)」というもので、オーストリアなどヨーロッパで開発が進み、日本でも西日本を中心に実用化が始まっています。文字通り木材を縦横に積層した強化木材で耐震性にもすぐれ、厚いものだと500mm、イギリスなどではすでに10階建てアパートなどにも応用されていて、今後注目されそうです。
聞いた話ですが、ヨーロッパで最初に鉄鋼船を開発したのはオランダで、木材不足に困って鉄の船を考え出したそうですが、大型建造物の木材回帰はこれまた面白い現象です。
(今月の書感)
「ウェブとはすなわち現実世界の未来図である」(ジョンレノ・ホツマ)/「習近平は必ず金正恩を殺す」(恵比寿っさん)/「医者の嘘」(致智望)/「おどろきの中国」(山勘)/「里山資本主義」(高幡童子)/「夜と霧―ドイツ強制収容所の体験記録」(狸吉)
(今月のネットエッセイ)
「プロフェッショナル」(本屋学問)/「『箱根』の語源」(ジョンレノ・ホツマ)/「『同胞(はらから)』の語源」(ジョンレノ・ホツマ)/「現代中国流の『学び方』」(山勘)
(事務局)
ウェブとはすなわち現実世界の未来図である/小林弘人(PHP新書 2014年発行)

著者はビジネス・ブルースクール大学教授でもあり、大前研一氏が同じ大学学長であることを知り、一読しておきたい気になりました。
聞きなれないカタカナ言葉など多く、理解するのに時間がかかりました。
最近始めたGメール・Googleについて多少疑問に思う所を感じていた矢先であったため、共感を持って読むことが出来ました。 結論はGoogleの動きから目を逸らすなという警告書のようにも捉えられました。
グーグルが無料で利便性を提供する理由について、著者は周りに気を配りながら遠慮しがちに述べられていますが、私流に言えば、野生の動物に対し、餌付けで誘き寄せ、餌付けに慣れてきたので、そろそろ自分の考え通りに思う存分采配が揮えるという流れのように見えます。
もちろんグーグル自身もそこまでは意識してないとは思いますが、今後、何をしようとしているのか、著者本人も気になり、広く語り掛けなければと思われたものと思います。
グーグルを語ることは未来を語ることという項目があり、グーグルの社是は“Don’t be evil.”(悪魔になるな)だ。とのことです。
彼らは自身のパワーをよく理解しているが、たとえ彼らが善だと思っていても、価値観は国や文化、資本力の差によって変わる。そして、彼らが引き起こす変化は、本人たちが想像している以上に大きな破壊力をもつ。と、著者は述べています。
更に、グーグルの善は私たちの悪か?と疑問を呈しており、その中で、テクノロジーの進歩は、私たちに力を与えた。しかし、皮肉なことにそれはネットワーク化された世界では非対称性をもつ。個々に力が分配されるとき、その分配者自身はさらに権益を集め、巨大化していく。グーグルは世界中からあらゆる最高の知性を集め、テクノロジーを駆使し、壮大なデザインを行なおうとしている。彼らの考える善が、ほかの人の悪にならぬよう祈るばかりだ。と、あります。
身近な具体例として、カーナビメーカーを苦しめるグーグルという項があります。
情報がオープンとなった社会での競合者は既存のライバル企業ではない。カーナビを例にとると、世界でもトップを走っていた国産カーナビ機器メーカーをいま苦しめている相手はグーグルだ。「カーナビ」というパッケージされた電子機器ではなく、グーグルマップをつかったネット上の地図案内サービスだが、ドライバーが自分のスマートフォンをダッシュボードに置けば、今までのカーナビは不要になってしまう。高価なカーナビを買う必要がなくなってしまった。
私自身、これに関連して驚いたのは、最近ごく普通のビデオカメラを購入したとき、Google Earth に位置情報を記録しながら撮影できるようになっていたことです。
地図以外にその場所の状況・ストリートビュー以外にも、ユーチューブの画面を見るかのように不特定多数の人が撮影した現地の動画を確認できることです。
ソーシャルナビというユーザーが渋滞や取り締まりなどを現在の情報を投稿し、リアルタイムの交通情報を地図上で共有するサービスもとりいれているようです。
さらに、グーグルではクルマの自動運転を目指しておりそろそろ実用化されるとのこと。グーグルマップやストリートビューで培った道路状況のデータと、リモコン操作のプログラムを融合させたものが本格化したら、今までのカーナビ以上の機能のものが出現することになる。
グーグルの買収傾向を見て、ウェブだけではなくテクノロジーと人間の未来を語ることは、グーグルの未来を語ることになる。
私はグーグルの全能的ともいえる拡大に全面的に賛同しているわけでもない。と、著者は述べられている。
私も、グーグルやGメールを使い始めて、あまりにも便利であるが、何事にも首を突っ込まれているようで、何か空恐ろしい感じを受けることがあります。
グーグルは量子コンピュータの開発にも資金を投下し、すでにNASAと共同で「量子人工知能ラボ」を創設した。量子コンピュータによって解析可能になると、先物取引や穀物相場などを何年後の何月何日のどの場所で行なうべきということがピンポイントで予測できる可能性もある。軍事、安全保障、経済など、ありとあらゆるものが変わってしまう。
ライフスタイルや社会生活まで関わってくるため、そこにはつねにある種の怖さがつきまとう。
(ジョンレノ・ホツマ 2014年12月8日)
習近平は必ず金正恩を殺す/近藤大介(幻冬舎新書 2014年8月28日 第一刷発行本体1500円)
著者略歴
1965年生まれ、埼玉県出身。東京大学卒業後「月刊現代」「週刊現代」「フライデー」などで記者・編集者を務める。
2009年から2012年まで講談社(北京)文化有限公司副社長。現在、「週刊現代」編集次長。
中国や朝鮮半島を中心とした東アジア問題の研究をライフワークとしている。
著書には『日中「再」逆転』、『対中戦略』(講談社)、『深紅の華』(廣済堂出版)、『中国人の常識は世界の非常識』(KKベストセラーズ)等がある。
目次
まえがき 北朝鮮が日本に接近する「お家事情」
第一章 中国人が金正恩をバカにする背景
第二章 習近平が金正恩を大嫌いな理由
第三章 張成沢粛清で激変する中朝関係
第四章 習近平が金正恩を殺す方法
第五章 中国が北朝鮮に戦争を挑む必然
タイトルに惹かれて予約。3カ月で図書館予約確保。意外と短期間で驚きでした。急速な中朝関係の悪化と、日本への接近(拉致問題)の背景が少しでも分かればという期待です。
で、(前書きにもあるように)
第一章では、金正恩が如何にバカにされているか
第二章では、険悪化する中朝関係を
第三章では、張成沢の粛清の真相に迫り
第四章では、14年の中朝関係について
第五章では、中国の(戦争相手として)標的候補は金正恩政権であると述べている。
筆者は、小泉訪朝の随行貴社経験があり、天安門事件以降一貫した中国関係を取材してきたチャイナウオッチャーで、日本から見るのではなく中国から見た現地経験やその情報チャネルから信憑性の高い記述と期待して読みました。
中国では、金正恩は「三代目のデブ」と蔑称されているが、これは、中朝関係の悪化から習が北朝鮮に関する限りにおいてNET空間を野放しにしているからである。
あれだけ蜜月関係にあった中朝だが、今や冷戦の時代。12年末のミサイルやそれに続く核実験。中止の(習の)申し入れに対し金はこれを突っぱねて強行。習は(これまでは三大援助してきたが)制裁を始めた。国連安保理の制裁に中国も同意。習は言う「大事なのは地域の安定で、北の現政権の安定ではない」(ケリー米国務長官へ)。
中国は本気で北の核保有に反対しているのに、北は国家の自由と言い、全く折り合いはない。
見はなすきっかけは両国を結ぶ懸け橋役だった張成沢(改革開放派)の粛清。「国家反逆罪」で公開処刑、最後まで金正恩に会わせれば誤解が解けると哀願していたそうです。100発近い機関銃で原形をとどめず、更に火炎放射機で焼くという残忍さ。中国での不正蓄財や金正男への資金援助は真実と思うがあとは政権によるでっち上げの感がしますね。
側近による暗殺の可能性や人民による暗殺、はたまた戦争の結果による死亡や自殺など、の可能性も上げている。また、中国内では経済援助をストップしているのに新鴨緑江大橋の建設は続行して完成。一説では解放軍戦車が通れるようにするためだと…。
これらを総括して、第五章では中国が北朝鮮に戦争を仕掛ける必然までも述べていて、興味深い。
また、習と軍は関係が必ずしも良くないとも本書は指摘している。中国側から見たら、北朝鮮の混乱で難民が中国流れ込んだり、或いは中国東北部の朝鮮民族(≒2M人)が独立運動を起こすようなことがリスク要因であるが、我々日本にとっても地域の安定は維持したいものです。とは言え、両国ともまともな国家として有って欲しいですね。
拉致問題の解決に向けて日本にとっては情勢は有利であるが、かつての血盟の中国をも今や敵国に回したり、身内まで粛清するガキが相手ですから、慎重に交渉する必要を改めて認識した次第です。
(恵比寿っさん 2014年12月8日)
医者の嘘/石井 光(幻冬舎 本体1,100円)
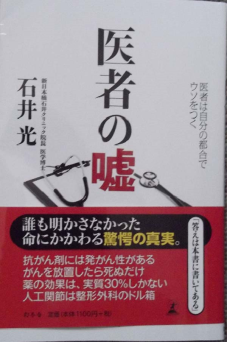 本書の副題として「医者は自分の都合でウソをつく」であり、表紙のキャッチには、「誰も明かさなかった命にかかわる驚愕の真実」とあります。
本書の副題として「医者は自分の都合でウソをつく」であり、表紙のキャッチには、「誰も明かさなかった命にかかわる驚愕の真実」とあります。
私は、医者から「脊柱管狭窄症」と診断され、10mも歩くことが出来なかった。その時、いい加減な手当しかしない医者、やたらと手術を進める医者がいる一方で、手術をしてはいけないと言う経験者の話などから、途方に暮れて困った。何を信じるかと言う心境に立ち至った時、真面目な若い医者に出会い、親身に手当をしてくれた医者に巡り会った。その時、本書のタイトルに引かれて読み始めた書である。
著者の石井光は、新日本橋石井クリニック医院の院長であり医学博士で、日本医科大学卒業後、米国留学、大学病院勤務などを経験し、1996年に医療法人社団光人会新日本橋石井クリニックを開設して今日に至っている。ご専門は消化器内視鏡で、年間約3000件の内視鏡手術をおこなって来た方だ。
大変研究熱心な先生で、ある事からコラーゲンの研究をはじめ、コラーゲンが骨や血管の健康と大きく関わっていることを知り、骨粗しょう症や動脈硬化などに素晴らしい効果があることがわかったといいます。これほど有用なコラーゲンのサプリが数多く販売されているにも関わらず、なぜその効果が表れないのかを調査してみると、コラーゲンサプリに大きな問題があり、大手メーカーは食品偽造と言ってもおかしく無い方法でサプリを製造していたと言います。
先生は、臨床成績を基に「血管が若返れば健康寿命はのびる」を出版したところ、整形外科や循環器の患者が全国から来院するようになり、専門の内視鏡だけでなく、多彩な患者を診察するようになったと言います。
主治医に人工関節を勧められたものの、先生の指導により不要になった人、数多くの薬をのんでいた患者が、薬の数を大幅に減らしたと言います。政府は国民医療費の削減に躍起になっていますが、先生からみると医者が不要な手術や薬を押し付けている現状こそ問題といいます。
9年程まえから、がんの免疫細胞療法に取り組むようになり、来院される患者はステージⅢとかⅣの患者ばかりで、何故か早期の進行がんの患者が来ないので、調べてみると、主治医は「そんな治療は未承認治療で無効だ」と言われるそうです。「それを受けるなら、もううちでは診ないといわれた」というのだそうです。だから先生のクリニックに来ることができなかったと言う。この様に毎日患者と接触しているうちに、医者の嘘が如何に多いかを知らされたと言います。
ここまでが、本書の「初めに」であります。
本文には具体的な事例が記述されております。「がん治療の嘘」、「がん予防の嘘」、「生活習慣病・老人病の嘘」、「健康診断・人間ドックの嘘」、「健康常識の嘘」「薬・サプリメントの嘘」、「日本医療の嘘」があります。
一つの例として、特に印象に残った記述を上げますと、ジェネリック薬に付いて述べられた記述です。後発薬のジェネリックと先発薬とは効き目が違うといいます。著者の先生は、絶対にジェネリックを使わないと言います。厚生省の役人は医療費の節約からジェネリックを使えと圧力をかけるが、そもそも、特許が切れた薬だからと言って、先発薬と同じものが作れるとは限らない、製造過程や原料まで公開しているわけではないので、同じ効果を見込める薬など出来る筈が無いといいます。
私も、何時も行く薬局にて試してみました。ジェネリックで無いものが欲しいといったころ、勘弁してくれと言います。所管の役所の縛りがあるのだそうです。
私が試した些細な例からも、石井先生の話は、恐ろしい事であります。
がん患者の治療は、診療の過程がすでに決まっていて、何処の医者も同じ治療しかしない。特に大病院は酷いものだと言います。有名な医者程実は何も出来ない、何々学部長などと言う博士が、何人もの手術経験など出来るものでは無い、良い医者は大学の有名医には居ないと言い切ります。良い医者は、結果の良い医者の事であり、完治した患者が発信する評判が一番と言います。
我々生身の人間です。何時なんどき患い人になるか解りません。常々心がけておく必要を改めて感じさせられ、何気なく不信を抱いて居たことが、やはりそうだったかと思わせる書でした。
(致智望 2014年12月8日)
おどろきの中国/橋爪大三郎×大澤真幸×宮台真司(講談社現代新書 本体900円)
題名は安直で近ごろ流行りの“嫌中本”を思わせるが、内容は、中国とどう付き合うべきかというテーマに、歴史を踏まえて真正面から取り組んだ硬派の学者談義である。
本論は4部からなり、「第1部 中国とはそもそも何か」では、古来、秦、漢、唐、明など制服王朝名で呼ばれ、中国という国名では呼ばれなかった歴史を考察し、2200年前の秦の始皇帝による統一帝国から、中華思想を軸にして異質の民族を取りこんで拡大してきた多民族国家の中国を分析する。
思想面では、法家と儒家に注目する。法家の発想は信賞必罰でルールと罰則で支配しようとし、それが強すぎた秦王朝は短命に終わった。儒家(儒教)は家族や親族の秩序を守るイデオロギーである。中国における歴代の統一政権は儒教を表に、法家を裏にしたダブルスタンダードでやってきた。
制度面では中国社会における「帮」(ほう)に注目する。これは仲間のためなら自分のすべてを犠牲にする覚悟で結束するグループで、典型的な例は三国志の劉備、関羽、張飛である。逆に言えば帮の外側は無法地帯にもなりえる。この帮が今日に至るまで中国における社会関係の核だと見る。
科挙と宦官では、皇帝(天子)は儒教の戦略によって血縁で継承されるが、それ以外は能力主義で、その典型が科挙によって選別された行政官僚だとする。宦官は去勢されて子孫にこだわらず皇帝や皇宮によく仕え、官僚を抑える。これが中国におけるリーダーとブレーンの「公理」だという。
「第2部 近代中国と毛沢東の謎」では、中国の近代化が遅れた理由、つまり1911年の孫文による辛亥革命から49年に毛沢東の共産党政権が成立し、文化大革命があって、鄧小平の改革開放を経て現在に至るが、その間、欧州的な近代化が大幅に遅れたのは、根本経典、テキストを持っていたからだという。イスラムならコーラン、インドならヴェーダ聖典のように、中国は経典(朱子学の四書五経)が社会制度や道徳の縛りとなって西洋流の近代化を阻害したとみる。
毛沢東については、鄧小平の改革開放は文化大革命を含めて毛沢東主義の全否定だが、にもかかわらず現在でも毛沢東の権威が持続している不思議について、彼は明、清二代の皇帝がいた天安門の上に立って新中国建国の宣言をしたことに始まって、伝統中国の皇帝イメージを最大限に利用して君臨したこと、その一方で、村々にまで農民や職場の「単位」を置き、党書記や工作隊を送り込んで学習会を開き、地主や反革命分子を排除し、大衆の政治参加を促進した点を挙げる。
「第3部 日中の歴史問題をどう考えるか」では、江戸時代までの日本には先生だった中国へのコンプレックスがあったが、第一次大戦時の対華21カ条要求あたりから日本が居丈高になった。さらに満州事変の当初は中国を味方につける構えだったが、盧溝橋事変から軍部の暴走がはじまった。南京事件は日中戦争の全体を隠喩的に圧縮しているとして、これを指揮した松井石根大将の英雄主義は日本の利益や欲望にも関係なかったとする。
そこで、中国が今日まで日本に謝罪を要求するのは、日本の「過去に対する構え」と「未来に対する構え」が曖昧だからだとする。過去に対しては、東京裁判におけるA級戦犯の指導や作戦が誤っていたことを認め、これを国民がよく認識していることを示し、未来に対してはその過ちを繰り返えさないという構えを示して謝罪し、信頼を築くべきだとする。それは東京裁判の示すところでもあり、日中国交回復時の日中共同宣言における田中角栄・周恩来の合意でもあるという。
「第4部 」中国のいま・日本のこれから」では、改革開放以降の鄧小平による「社会主義市場経済」とは、社会主義経済=計画経済の枠内における商品に限った市場経済であった。商品のほかの土地、労働、資本の市場化は除かれたが、徐々に都市部の労働者で労働市場化がはじまった。
しかし、中国が民主主義市場経済になったり米国に代わって世界の覇権国になることはないとみる。日本はこれからも米国側に立たざるをえないが、台湾問題、北朝鮮問題などで独自の判断を持ち、米中双方の関係改善のうえで、日本を仲介役にする利点を認められる力を持つべきだという。中国寄りの論拠が強いきらいはあるが、中国を見る目のうろこが一枚剥げる思いのする一書だ。
(山勘 2014年12月13日)
里山資本主義/藻谷浩介・NHK広島取材班(角川ONEテーマ21C‐249)
筆者 藻谷浩介は1964年、山口県生まれ。日本総合研究所主席研究員。著書「デフレの正体」は50万部のベストセラーとなり、生産年齢人口という言葉を定着させ、社会に人口動態の影響を周知させた。他に、「実測!ニッポンの地域力」(日本経済新聞社)等がある。
競争の中で猛烈に働き、猛烈に稼ぎながら、結果としてたいした豊かさを実感できず「不安と焦燥」のなかであくせくする「マネー資本主義」から脱することを筆者は提案している。
人類のすべての努力、苦楽、幸不運がいったん「マネー」の形に集約されたあと評価され再配分されるメカニズムでは、高度に専門化したマネーがマネーを支配し、少数の勝者と多数の負け犬、そして双方に残る「不安と焦燥」の連鎖を断ち切れない。
筆者はリーマンショックを例にとり、「マネー資本主義」の無益さを説く。
代わって筆者が提案するのが中国山地のあちこちで始まっている「里山資本主義」である。利用されず、手入れされず、山崩れの元になっている山地の有効利用、いや山地が主体となる人間の暮らし方である。植林を行い、手をいれて育て、運搬用ワイヤー、分散型製材所、農林専門学校、国家資格試験制度を整備する。適正な人口密度の村落と自給自足が日本国の主体となる。燃料の石油依存度を減らし、木製チップに置き換える。自給自足が増えるため、国家、国際貿易でのマネーの比重は大幅に下がる。国の政治も道州連邦制とし、自給自足の家族を含め、自治体の権限と責任を高めていく。
このような本を読むと「不安と焦燥」が消え、「希望」がわいてくるが、実現性への「疑問」も沸いてくる。筆者は燃料チップ、人口動態の分析、オーストリアの例を引いて、決して夢物語ではないと主張している。
(高幡童子 2014年12月16日)
夜と霧ードイツ強制収容所の体験記録 V.E.フランクル著 霜山徳璽訳
(みすず書房2002年1月新装28刷 本体1800円)
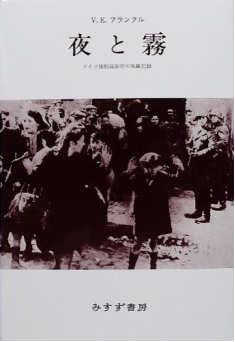 本書はドイツ強制収容所内の体験を描いたドキュメンタリー文学の名作として、世界17ヶ国語に翻訳され、今日まで60年以上読み継がれている。日本でも単行本や文庫本の体裁で数人が翻訳している。今回読んだ本は初版(原著1947年、1956年日本語版刊行)と同じ内容だが2002年には著者自身の手による改訂版が出版され、日本語にも翻訳されている。
本書はドイツ強制収容所内の体験を描いたドキュメンタリー文学の名作として、世界17ヶ国語に翻訳され、今日まで60年以上読み継がれている。日本でも単行本や文庫本の体裁で数人が翻訳している。今回読んだ本は初版(原著1947年、1956年日本語版刊行)と同じ内容だが2002年には著者自身の手による改訂版が出版され、日本語にも翻訳されている。
著者はユダヤ人としてウィーンで生まれた著名な精神科医。訳者も同じ精神科医で、生前の著者を訪ね親しい仲となった。
本書の構成はいささか風変わりだ。冒頭に出版社の序文があり、本書出版の意義、著者・訳者・資料提供者への感謝の辞が述べられている。それに続いて、強制収容所を企画・運用した人間から、所内の日常に至るまで、訳者が書き下ろした68ページもの長い解説が付く。巻末には訳者後書きと共に強制収容所や死体など、45点の写真や図版が関連資料として添えられている。これらはいずれも原著には無く、訳者・出版社の本書刊行に対する意気込みが伝わってくる。
解説の中で語られる、収容所の劣悪な生活環境、日常的に繰り返される残虐行為、囚人の殺戮方法など、読んでいるうちに気分が悪くなる。実は私(狸吉)も、初めて本書を手にしたとき、読み続けられず、一年以上経った今、書感を書くため再び読み始めた次第である。NET上に誰かが書いていたが、繊細な神経の持ち主にはあまり勧められない。
本書は大きく分けて三部から構成されている。まず導入部では、ユダヤ人、ポーランド人、戦争捕虜、その他政権が危険と判断した人々が日常生活から突如引き離され、収容所に送り込まれる様子を描いている。強制収容所に送り込まれると、体力のない老人・子供・女性はガス室で殺され、残りはわずかの食料と劣悪な環境下で重労働を課せられ、緩慢な死に追いやられる。囚人たちは肉体的・心理的な衝撃を受け、興奮し、恐れおののき、悲嘆に暮れるのだ。
次いで囚人たちが日常的に、監視兵の理不尽な暴行に晒され、次第に無気力・無感情になって行く過程が描かれる。やがて囚人の中から監視兵に対する協力者が現れ、囚人仲間を積極的に虐待し、それを楽しむような状況も出現する。医師や看護師の資格を持った囚人は収容所内の診療所で働かされたが、何と彼らが仲間の囚人たちに毒薬を飲ませたり、生体実験をしたのだ!これらの残虐行為はあまりに非道で、ここに書き写すのも憚られる。
この状況下にあって著者は、「人はすべて外的な条件で心を失い、囚人らしい囚人に堕していくのか?」と問い、自らの体験から「いや決してそんなことはない。極限下の状況にあっても高潔な志を保つ人々は存在する」と断ずる。そしてその具体例として、稀に見る人間的な監視兵、自分の金で囚人に薬を買い与える収容所長、仲間のために貴重な食料を差し出す囚人などを挙げている。圧制者の中にも善人は存在し、囚人の中にも悪人は存在する。また一人の人間の中にも、善と悪は混在し、簡単に善・悪を断定しがたいと説く。この冷静な思考様式は、心理学者で精神科医という著者の職業からくるのであろう。
最後は侵攻する連合軍による収容所からの解放と、日常生活に戻った人々が心理的囚人状態から脱却する過程と苦悩を描いている。「クリスマスまで解放される」との噂に喜んだ人々が、少し遅れた救出の前に、「やはり噂に過ぎなかったか」と落胆し大勢が死んだ。ここでも著者は「人は絶望によって死ぬ。未来に希望を持つ者だけが生き延びる」と冷静に観察している。
しかし、狸吉は「希望だけでは無理。神仏のご加護が要る」と感じた。ことに収容所解放の夜、証拠隠滅のため、生き残りの囚人を親衛隊が欺いて連れ出し、全員を焼き殺したとき、トラックが満員で著者が取り残され生き延びたエピソードなどは、正に奇跡としか言いようがない。きっと神がナチスの戦争犯罪の告発者として著者をこの世に残したのに違いない。
読後「さて自分がこれと同じ状況下に置かれたらどうだろうか?」と自問し、「たぶん、助かりたい一心で監視兵の走狗になっただろう」と思い、恥かしくかつ情けない気分になった。日頃出会うことの稀な、心にずしりと響く重い本であった。この本を読んだことは生涯記憶に残るであろう。
(狸吉 2014年12月17日)
プロフェッショナル
演奏会でも演劇でも何でも、本番前の稽古は当たり前である。とくに厳しい指揮者とか演出家になると何日もかけて念入りに行なうそうで、素人はもちろん、プロの演奏家でも俳優でもそれは同じことであり、本番にベストの状態で臨むためには当然のこととして、誰もが少しも疑問に思わない。
ところが先日テレビを観ていたら、能の世界ではほとんど稽古のようなことをやらず、「申し合わせ」といって前日に出演者が1回だけ顔を合わせてリハーサルをするだけだという。これが能楽だけの慣習なのかどうかはわからないが、シテやワキといった舞台の主役たちをはじめ、笛や太鼓、鼓を担当する囃子方、地謡、後見、合わせて20人ほどだろうか、彼らは毎回、文字どおり “ぶっつけ本番”で臨むのだそうだ。つまり、全員がその演目を知り尽くしているということか。ただし、その本番の出来の良し悪しが私たちにはわからないのが残念ではあるが。
ジャズやロックの世界では「ジャムセッション」というのがあって、初めて顔を合わせたミュージシャンたちがその場でバンドを組み、即興の演奏表現の妙を競う。それでも名人プレーヤーたちが集まればたちまち“一期一会”の素晴らしい演奏になり、録音されたものが世紀の名盤として聴き継がれているのだからさすがである。名人芸というのは、演奏の完璧さとか卓越した技法はもちろん、どれだけ人の心を揺さぶるかに尽きる。
プロフェッショナルといわれる人たちは、どんな場合でもすぐに対応できなければならないし、それができなければプロではない。その意味では能楽者やジャズミュージシャンたちは、まさにプロ中のプロといえるのかもしれない。
クラシック音楽の世界でも、そんなエピソードには事欠かない。名指揮者トスカニーニはオーケストラのチェロ弾きだったが、演奏旅行であるとき指揮者が急病になり、急遽代役として指揮台に上がり衝撃的なデビューを果たした。ニューヨークフィルのアシスタント指揮者だったレナード・バーンスタインは、ブルーノ・ワルターが風邪を引いて指揮ができなくなったとき見事に代役を務め、一夜にしてシンデレラボーイになったことは有名な逸話だ。
どこかで読んだ話だが、アポロ計画全盛の頃、打上げ直前にコンピュータが不具合になっても、NASAのベテランが直感的に“カンピュータ”でトラブル箇所を推定して探し出し、数時間後には立ち直ったそうである。しかし、そうしたプロがいなくなると、3日間かけて全体をコンピュータでシミュレーションし直して故障を発見する方法しかなくなった。
良くも悪くも終身雇用が定着している日本では、中途採用はとかく差別されがちだが、実は入社したすぐその日から仕事をこなせ、スキルも十分に備えているのがプロフェッショナルである。原子炉事故、製鉄所や化学プラントの火災、自動車のリコール、新聞の誤報問題、医療ミス…。最近の日本は明らかに社会の劣化が進んでいるが、それはこうした分野に本当のプロが少なくなったこともあるのではないか。
そんな日本の現状のなかで今そこにある最大の危機は、間違いなく政治のプロフェッショナルがいないことである。そもそもの責任は、彼らをド素人のまま政界に送り出し、あまりにも甘やかせ過ぎた私たち国民やマスコミにあるが、今の選挙制度がどんなに無能な人間でも国会議員になれるシステムをつくってしまったことも大きい。政経塾で何を学んだのか国政にそれをほとんど反映できなかった議員、40年も政界にいながらまったくOJTを実践できなかった議員、世襲の悪い面だけを受け継いだ議員……。
何千億円もの税金を使う国の最高議決機関が、一般社会ではほとんど使い物にならないこんな人たちを救済するための “福祉システム”と化していていいのか。真のプロフェッショナル政治家を育成するために、現実的にどのような方法があるのか、改めて真剣に考える必要があるのではないだろうか。
(本屋学問 2014年12月5日)
ホツマツタヱ24綾に、箱根の語源がありましたので紹介します。合わせて「はらから」(同胞)の語源も同じところにありました。
箱根の由来は、「箱根神社」に祀られている御祭神の「箱根神」からきています。では、この「箱根神」とは誰のことでしょうか。
「天照神」と「さくなだり・せおりつひめ・ほのこ」(通称、むかつ姫)との間に生まれた子供の「おしほみみ」(天忍穂耳尊)のことであることが分かります。なぜ「箱根」という名前が付けられたという話になります。「おしほみみ」が死ぬ直前に自らを「箱の根」と名付けられたことが記されています。
「おしほみみ」は、生まれながらにして体が丈夫でなかったため、寒い時期には禊ぎも真似をするだけで済ませていたという記述があります。
父の「天照神」と比べても、息子の「はら」親王・(天孫ニニキネ)と比べても、今まで私が読んだ範囲には、活躍した記載は見当たりません。あまり表に出ることがなかったのは病弱であったことが容易に推測されるからです。
以下、24綾の内容を抜粋して現代風に書き換えてみました。
晩年、帝(おしほみみ)は二人の皇子を日高見宮(今の仙台地方)へ召されるよう伝えられて宮入りしました。そこで、父である帝(おしほみみ)は、二人の皇子に詔りをしました。
「私は年を取り老いてしまいました。今後、兄皇子を大和飛鳥親王と命名します。弟皇子を「はら」親王と命名します。二人は、お互いに仲たがいすることなく共に睦まじく民を守りなさい。」
「大和飛鳥親王よ、弟「はら」親王よ、しっかりと聞きなさい。国民を決して我が物(私物化)してはいけません。君は国民の園であり、民のための君です。
「た」(父)は、箱の中の根っこです。自分(父・おしほみみ)は陽の目を見なかったので、子供二人には二枝の恵みを受けて、陽の目を受けて万人を愛でてください。私は邪欲もないし、二心もありません。
神の鏡である天照神の日嗣の君として、私(おしほみみ)は箱の根となり、二人が二本の枝となって、地上で民を守っていけるよう見守ります」
その後、寿命が尽きると悟った「おしほみみ」は、伊豆雄走山に洞穴を自ら掘り、箱根神となられました。
「はら」親王・(天孫ニニキネ)は、箱根神を「いづさきみや」(伊津崎宮)に3年間祀りましたとあります。
時代と共に風化されてしまい、現在箱根神社の御祭神は、ご本人の「おしほみみ」(天忍穂耳尊)ではなく、息子(弟の方)の天孫ニニキネ(瓊々杵尊・ニニギノミコト)とそのお妃の「このはなさくや姫」(あしつ姫)・(木花咲耶姫命)と、二人の間に生まれた三つ子の末っ子の「ひこほほでみ」(うつきね)・(彦火火出見尊)になっています。
正に、箱の根から表に出て枝となり開花したこと、つまり親が出来なかったことを自分の息子夫婦と孫が成し遂げてくれたことを「おしほみみ」(天忍穂耳尊)も納得され喜んでいることと思いました。
(ジョンレノ・ホツマ 2014年12月8日)
ホツマ・エッセイ 同胞(はらから)の語源
同胞(はらから)とは、兄弟とか、文字通り同じ母親から生まれた兄弟という意味ですが、ホツマツタヱの24綾の中から、この「はら」には元々の語源になる経緯の意味合いが含まれていたことが分かりました。
箱根神の遺言により、二人の兄弟が睦まじくしていくために、もし、二民(兄「飛鳥親王」の民と、弟「はら親王」の民)の間で、争い事が起きた場合は、臣を遣わして和睦するよう裁きましたが、何事も兄の大和の臣民を立てることでした。
そのために弟「はら」親王の治めている新治の民側に損失が出るようなときは、弟「はら」親王の方から埋め合わすようにしました。
その結果、この二人の皇子(親王)の代のときは、争い事があっても、常に弟「はら」親王の方から歩み寄って兄の方の言い分を呑んでいたため、表面化せず、いつも睦まじく見えたので、この二人の「え」(兄)「と」(弟)のことを「はらから」というようになりました。
ここで「はらから」は現在では、同胞という漢字が当てはめられており、文字通り、「同じ母親のお腹から」という意味合いになっています。
しかしながら、本来は、弟の「はら親王」が譲って事が治まっていたことが元の語に含まれていたことが分かります。
「はらから」の「はら」は、「はら親王」を意味していたからです。
(ジョンレノ・ホツマ 2014年12月8日)
おどろきの中国/橋爪大三郎×大澤真幸×宮台真司(講談社現代新書 本体900円)
題名は安直で近ごろ流行りの“嫌中本”を思わせるが、内容は、中国とどう付き合うべきかというテーマに、歴史を踏まえて真正面から取り組んだ硬派の学者談義である。
本論は4部からなり、「第1部 中国とはそもそも何か」では、古来、秦、漢、唐、明など制服王朝名で呼ばれ、中国という国名では呼ばれなかった歴史を考察し、2200年前の秦の始皇帝による統一帝国から、中華思想を軸にして異質の民族を取りこんで拡大してきた多民族国家の中国を分析する。
思想面では、法家と儒家に注目する。法家の発想は信賞必罰でルールと罰則で支配しようとし、それが強すぎた秦王朝は短命に終わった。儒家(儒教)は家族や親族の秩序を守るイデオロギーである。中国における歴代の統一政権は儒教を表に、法家を裏にしたダブルスタンダードでやってきた。
制度面では中国社会における「帮」(ほう)に注目する。これは仲間のためなら自分のすべてを犠牲にする覚悟で結束するグループで、典型的な例は三国志の劉備、関羽、張飛である。逆に言えば帮の外側は無法地帯にもなりえる。この帮が今日に至るまで中国における社会関係の核だと見る。
科挙と宦官では、皇帝(天子)は儒教の戦略によって血縁で継承されるが、それ以外は能力主義で、その典型が科挙によって選別された行政官僚だとする。宦官は去勢されて子孫にこだわらず皇帝や皇宮によく仕え、官僚を抑える。これが中国におけるリーダーとブレーンの「公理」だという。
「第2部 近代中国と毛沢東の謎」では、中国の近代化が遅れた理由、つまり1911年の孫文による辛亥革命から49年に毛沢東の共産党政権が成立し、文化大革命があって、鄧小平の改革開放を経て現在に至るが、その間、欧州的な近代化が大幅に遅れたのは、根本経典、テキストを持っていたからだという。イスラムならコーラン、インドならヴェーダ聖典のように、中国は経典(朱子学の四書五経)が社会制度や道徳の縛りとなって西洋流の近代化を阻害したとみる。
毛沢東については、鄧小平の改革開放は文化大革命を含めて毛沢東主義の全否定だが、にもかかわらず現在でも毛沢東の権威が持続している不思議について、彼は明、清二代の皇帝がいた天安門の上に立って新中国建国の宣言をしたことに始まって、伝統中国の皇帝イメージを最大限に利用して君臨したこと、その一方で、村々にまで農民や職場の「単位」を置き、党書記や工作隊を送り込んで学習会を開き、地主や反革命分子を排除し、大衆の政治参加を促進した点を挙げる。
「第3部 日中の歴史問題をどう考えるか」では、江戸時代までの日本には先生だった中国へのコンプレックスがあったが、第一次大戦時の対華21カ条要求あたりから日本が居丈高になった。さらに満州事変の当初は中国を味方につける構えだったが、盧溝橋事変から軍部の暴走がはじまった。南京事件は日中戦争の全体を隠喩的に圧縮しているとして、これを指揮した松井石根大将の英雄主義は日本の利益や欲望にも関係なかったとする。
そこで、中国が今日まで日本に謝罪を要求するのは、日本の「過去に対する構え」と「未来に対する構え」が曖昧だからだとする。過去に対しては、東京裁判におけるA級戦犯の指導や作戦が誤っていたことを認め、これを国民がよく認識していることを示し、未来に対してはその過ちを繰り返えさないという構えを示して謝罪し、信頼を築くべきだとする。それは東京裁判の示すところでもあり、日中国交回復時の日中共同宣言における田中角栄・周恩来の合意でもあるという。
「第4部 」中国のいま・日本のこれから」では、改革開放以降の鄧小平による「社会主義市場経済」とは、社会主義経済=計画経済の枠内における商品に限った市場経済であった。商品のほかの土地、労働、資本の市場化は除かれたが、徐々に都市部の労働者で労働市場化がはじまった。
しかし、中国が民主主義市場経済になったり米国に代わって世界の覇権国になることはないとみる。日本はこれからも米国側に立たざるをえないが、台湾問題、北朝鮮問題などで独自の判断を持ち、米中双方の関係改善のうえで、日本を仲介役にする利点を認められる力を持つべきだという。中国寄りの論拠が強いきらいはあるが、中国を見る目のうろこが一枚剥げる思いのする一書だ。
(山勘 2014年12月13日)