習近平と中国の終焉/富坂 聡(角川マガジンズ角川SSC新書 本体780円 2013年1月5日 第1刷発行)
 1964年愛知県生まれ。北京大学中文系に留学したのち、週刊誌記者などを経てジャーナリストに。中国現地の豊富な人脈を活かした取材力に定評があり、中国に関するインサイドレポートを多数手がける。
1964年愛知県生まれ。北京大学中文系に留学したのち、週刊誌記者などを経てジャーナリストに。中国現地の豊富な人脈を活かした取材力に定評があり、中国に関するインサイドレポートを多数手がける。
1994年、『龍の伝人経ち』で21世紀国際ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。
現在、「文芸春秋」「週刊文春」等への執筆のほか、テレビのコメンテーターとしても活躍中。著書に『中国人民解放軍の内幕』『中国の地下経済』『中国マネーの正体』『中国と言う大難』など多数。
はじめに
プロローグ 習近平指導部の誕生
第1章 「薄煕来事件」が習近平政権にのこしたもの
第2章 なぜ習近平が総書記に選ばれたのか
第3章 「格差問題」と「民主化の模索」
エピローグ 習近平時代の中国を読み解くために
中国社会を支配しているのは、社会主義的な平等ではなく、自由競争が生んだ格差である。平等と格差が共存できる社会は、富から取り残された人々が寛大さと忍耐で現実を受け入れるほかない。だが、その寛容さと忍耐は限界に来ており、群体事件は年間20万件とも30万件とも言われている。
このような事態を前に、中国共産党は更にその先を恐れている。(と筆者は述べているが、私に言わせれば、更に大きな問題は腐敗である。共産党が政治だけでなく経済をも支配している中で、甘い汁を吸っているのが党の幹部であり、そのことは国民のだれもが承知している。だから、やり場の無い市民は群体事件を起こすのである。)
この本は、200ページにも及ばない新書本であるが、今の中国事情を新しい視点で捉えていて面白い。日本人が中国を語る時には(日本人の国民性かもしれないが)公式化と単純化が先走ってしまって的を射ないことが多いが、著者は独自の観点で分析している。
天安門事件の時に、留学していて現場に居合わせたこともそういう視点づくりに影響していると思う。習近平体制を読み解く上で重要なのが、薄煕来の失脚と汪洋が常委入りしなかったことだと言う。即ち、新体制は凡庸な人事であったと言うこと。つまり、党や国が滅ぶかもしれないという危機意識を持ちながらも、相変わらず党の正しさと党の指導が最高位という矛盾の抱えての体制発足である。新指導部が抱える不安は何なのか、を論じている解説書と言える。
第1章では、薄煕来の事件が何故重大なのかと新政権の抱える最大のリスクについて述べている。薄が共産党の組織伝統である「低調」の価値観に挑戦したことが注目される。国民の人気を得るのではなく、共産党の上司や組織の要求に過不足なく信頼を得ることであるが、薄は07年の常委から漏れて重慶に左遷されたのを機に、打墨と唱紅運動を展開した。
市の公安副局長を死刑にしたりして市民の喝さいを浴びたり、革命歌を歌う運動で貧しかったけど今よりも平等で夢のあった革命時代を市民に植え付けて、次代の国家主席とまで囃され始めていた。打墨は正義の行為であるが、薄は人民に見せてはいけない道を見せてしまったので、中央は大きな危機感を持ち、妻の英国人殺害への関与を機会に抹殺に動いた。権力闘争などと言う生易しいものではないと筆者は語っている。
第2章では、習がトップに選ばれた理由として①誰もが反対しない人材である②父親と胡耀邦の関係、だと歴史の連続性を言っている。習にもアキレス腱があり、米ブルームバーグの暴露記事で報じられたとおりである。
第3章では、中国共産党は民主化を模索していることを、歴史を追って論じている。古くは天安門事件の引き金となった胡耀邦・趙紫陽が民主化を率いたが、鄧小平から見れば急進的であった。共産党は実は国民を意識して政策を行っている、人民を恐れている。なぜなら、民主主義国家では選挙があるので国民に責任があるが、中国では自分たち(共産党)だけの独裁なので、全ての責任があるから。
最後に、胡耀邦が残した2つのねじれがあると筆者は言う。
①自由な空気の中でデモを起こすと却って民主化にブレーキをかけてしまうこと
②息づき始めた民主化の機運を人民が無理に心の奥に抑え込まなければならなくなった、と。
しかし、今後、胡耀邦の影響力を無視できない、とも言っている。
なお、尖閣は日清戦争のごたごたの中で日本が掠め奪ったというのが中国の主張で、これを奪い返すことが共産党の存在価値に係る問題になっているのは、中国の暗黒の近代史に触れてしまったことだからだと筆者は言う。
(恵比寿っさん 2013年6月3日)
メキシコからの手紙/黒沼ユリ子(岩波新書 定価630円)

著者の黒沼ユリ子は、音楽コンクールの優勝歴を持つバイオリニストであり、ソリストとして活躍する傍ら、メキシコで音楽教育の学校を主幹し実績を上げている。
著者は、プラハ音楽アカデミーに留学中にメキシコの学者と学生結婚し、1児の母となり家族3人で、ご主人がメキシコ政府から委嘱された任地のオフェトラに赴くところから本書は始まる。その後、著者のご主人が急逝することになるが、愛するメキシコにて生涯を送っていて、その行動が日本政府、皇室から強い信頼を得るに至っている。
メキシコは米国と地続きの国であり、気候温暖でトロピカルフルーツやコーヒー、ココアの原産地である。このメキシコが何故に貧困と治安の悪さに苦闘しているのか、このメキシコの宿命について、著者の身を徹した情熱の経験を本書に表している。
メキシコには、ピラミッドや遺跡が沢山ある。16世紀に金銀を目当てにやってきたスペインの征服者達が、マヤ文明を引き継いだアステカ帝国を滅ぼしたからである。征服者達の記録によると、「ここには、(当時のスペインの)グラナダやセビリアの町にもないように大きな、世界中の物が何でもそろっている市場があり度肝をぬかれた」と日記にのこされている。そして、巨大な絵柄を地上に残しているナスカ文明。この驚くべき行動力や創造力なども、現代に残っていて話題になっている。
スペインがアステカ帝国を征服したとき、この地には50を超える言葉の違う少数民族が暮らしており、これ等の民族を全て「インディオ」とか「インディヘナ」という、一つのカテゴリーに押し込めてしまい、おのおのの独自性は無視されてしまった。そして、言葉はスペイン語に統一されたのである。この不幸が、メキシコの現在に至っていると著者は言う。原住民は、土地や農産物を支配していても、言葉の問題で酷い目に合わされており、メキシコ政府もこの少数民族の対策に手を差し伸べ、政府直属の対原住民機関の改善を大統領が謳い、著者のご主人も政府の委嘱を受けてオフェトラに赴く事になったのである。その地でおこる原住民と著者3人の家族の生活体験がきされている。
政府のお題目は立派なのだが、言葉の判らない原住民から取り上げた土地は、スペインの統治時代からのもので、複雑な事情がからんでいる、今の時代になると現地住民とスペイン人との混血が進み、インディヘナと白人の区別は付かなくなっている。問題は、公用語のスペイン語を理解できるかどうかで、差別が深刻化し、原住民問題として選挙の主題になっている。その人脈構図は既得権が絡み政府の役人もからんで、一筋縄では行かない矛盾を抱えており、著者のご主人はその矛盾のなかで、家族の生命にまでも及びかねない状況に、任務の撤回を申し出ることになるのである。
我々の知らないメキシコの不幸な歴史によって、本来文明国の一角を担う条件を備えたメキシコであるが、暫くは現代文明の蚊帳の外に置かれるのではなかろうか。
(致智望 2013年6月5日)
Sweet Poison スイート・ポイズン/ジャネット・スター・ハル著・吉 田三知世訳(東洋経済新報社 2013年2月発行 本体1800円)
田三知世訳(東洋経済新報社 2013年2月発行 本体1800円)
大学の教員であった著者はダイエット飲料を飲み始めてから、頭痛を起こすようになり、ダイエットどころか逆に水太りの症状が現われてしまいます。更に、アレルギー症状を起こし、瀕死の状態にまでなり、診察の結果、甲状腺の病気でバセドー病と診断され、甲状腺を放射線で破壊するしか、他に道は無いと診断され、必死に自分自身を振り返り、真の原因を見つけ出し、完治に至った経緯が書かれています。
ダイエット飲料を飲み始めた直後に片頭痛を起こしていたことに気が付き、そのダイエット飲料のラベルを詳細に見て、そのなかのアスパルテームという人工甘味料が病気の原因であったことを突き止め、このアスパルテームという人工甘味料の現状を詳細に調べ上げ、問題を投げかけています。
アスバルテームという人工甘味料は、ダイエット・ソーダなどのソフトドリンク、粉末食品、プレスミント、シリアル、チューインガム、ココアミックス、冷凍デザート、ゼリー、ジュース、下剤、チュアブル・ビタミンサプリ、乳飲料、調合薬や市販薬、シェークミックス、卓上甘味料、お茶、インスタントコーヒー、トッピングミックス、ワインクーラー、ヨーグルトなどに使われている。
アスパルテームという人工甘味料はアスパラギン酸とフェニルアラニンという2種類のアミノ酸とメチルアルコールとを結合させたもの。白い結晶性粉末。砂糖の180~220倍の甘味を持つ。1965年、アメリカで開発された合成甘味料で、アメリカ、カナダ、フランスなど20カ国以上で使用が認められている。米国食品医薬品局(FDA)の審査では、経口摂取されたアスパルテームの大部分が分解も代謝も受けずに体外に排泄されるという結果が出ている。従って、生理的熱量は極めて小さく、また調味料として普通に使う量では急性毒性や慢性毒性の問題が起こらないと解釈されている。
日本生活協同組合連合会などは、安全性への懸念などからアスパルテームを含む食品の取り扱いを行ってこなかったが、2002年3月に留意使用添加物から除外することに決め、取り扱い制限を解除した経緯があります。
今日、世界中で行なわれている科学的な研究から、アスパルテームという人工甘味料は、がん、記憶障害、出生異常、白血病、リンパ腫を引き起こすことが証明されており、多くの現代病はアスパルテームの使用に関連があると考えられるが、情報として消費者には今まで届いていなかった。
これは情報戦争であり、健康と利益の衝突、消費者、政治家、そして製造業者の対立が潜んでいます。アスパルテームが、それぞれの食材にはごく微量ではあっても、ありとあらゆる食材に使われており、塵も積もれば山になることに気がついて、表示には注意して、そのためには、出来るだけ加工食品を取らないよう、自然食品を取るように心がけることを生活の知恵にすべきと認識しました。
(ジョンレノ・ホツマ 2013年6月11日)
検察崩壊 失われた正義/郷原信郎(毎日新聞社 本体1,300円 2012年8月)
 検察は一般的には正義のシンボル、良心の府としてイメージされているが、実は権謀術数渦巻く腐敗に満ちた一官僚組織にすぎないことを、いわゆる“ヤメケン”だが、検察捜査の実態や裁判所の不当判決を最もよく知る立場にあり、追及を続ける著者が“法治国家最大の危機”として暴き出している。
検察は一般的には正義のシンボル、良心の府としてイメージされているが、実は権謀術数渦巻く腐敗に満ちた一官僚組織にすぎないことを、いわゆる“ヤメケン”だが、検察捜査の実態や裁判所の不当判決を最もよく知る立場にあり、追及を続ける著者が“法治国家最大の危機”として暴き出している。
検察庁内部の不正行為に対して指揮権発動も考えた元・法務大臣の小川敏夫氏、政治資金管理団体の記載ミスで有罪判決を受けた衆議院議員の石川知裕氏、郵便物割引不正事件捜査で証拠改ざんした検事の上司として責任を問われた元・大阪地検特捜部長の大坪弘道氏、それらの捜査段階で証拠隠滅や虚偽調書、報告書を書いた検事たちを告発した市民の会代表、八木啓代氏の4人が著者と対談する形で登場し、堕落し切った日本の検察機構の現状を告発する興味深い書である。
厚生労働省の局長が大阪地検に不当逮捕された第三種郵便物割引不正事件では、捜査担当検事が証拠品を改ざんするという信じられない行為をし、大坪氏は直接の責任はないものの懲戒免職となった。一方、東京地検が当時は野党第一党だった民主党の小沢一郎議員の資金管理団体「陸山会」の記載ミス問題を捜査したケースでは、供述調書にはない当時は秘書だった石川議員の嘘の捜査報告書を書いた検事や、一旦は不起訴となったこの案件を強引に検察審査会に起訴議決させるために虚偽報告書を書いた検事は、最高検報告書でも単なる記憶違いと記載され、大坪氏とは対照的にきわめて軽い処分で済んでいる。
これらの恣意的な判断は、まさに検察の組織的犯罪だと本書は糾弾する。担当検事はまた、この程度の内容なら共謀は成立しないと石川議員を説得して供述調書に署名させ、実際にはそれを共謀の最大証拠にしたという。この検事が書いた虚偽報告書はネットで見られるが、石川氏が取調べ中に密かに持ち込んだICレコーダのおかげで正確な反訳書がネット上に載せられ、報告書との違いが明らかになったもので、逆に検事の供述調書の信頼性が問われ、皮肉にも取調べの録音化、可視化の合理性を証明することになった。
起訴議決のために検察審査会に提出された検事の捜査報告書には、実際にはその事実はないにもかかわらず「石川被告が5000万円を受理した事実がある」と虚偽の記載をしたというのだから、何をかいわんやである。1人の有力政治家を陥れたいという妄念に駆られた一部の検察官が、検察審査会という外部機関を使って犯罪をでっち上げ、政治的影響を与えようとしたというのである。
著者は、この事件を検察のクーデター、民主主義を踏みにじる平成の二・二六事件といってはばからない。まさに戦前の軍部の暴走を彷彿とさせ、一部の検察官が反逆行為をしても組織としてまともな対処ができず、組織の統制が働かない状態だというのだ。検察官の証拠改ざんや供述調書、捜査報告書の虚偽記載は、十分に特別公務員職権乱用罪や虚偽有印文書作成罪に相当すると専門家はいうが、この実にでたらめで不自然な検察内部の処分に疑問を持つ人々はそれほど多くはない。
「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」の八木代表によれば、記者会見で1人のジャーナリストが検察官の起訴を迫ると、最高検幹部が「誰か告訴する人でもいるのか」と挑発的だったので、ツイッターで呼びかけたら研究者や企業家、行政書士、ジャーナリスト、編集者、主婦など数十人が手を挙げたそうだ。そこで市民の会は不正にかかわった検事たちを公務員の犯罪として告発したが、政治資金記載ミスでせいぜい罰金刑が妥当という陸山会事件ではあれほど起訴に熱心だった検察と検察審査会が、これだけ悪質な身内の犯罪にはまったく関心を示さず、結局彼らを起訴することはなかった。
法務大臣の指揮権とは、検察庁法に基づいて検察官を指揮監督するものだが、個々の事件の取調べまたは処分については検事総長に対してのみ発動される。自身が判事、検事、弁護士の経験を持つ小川敏夫氏が大臣退任会見で語った、検察内部の組織的不正に対して国民が納得できる十分な捜査を指示するための指揮権発動発言をマスコミは一斉に批判したが、その意味を熟知している小川氏の真意は、検察の自浄作用が期待できない今こそ発動すべきと考えたのかもしれない。小川氏はそのことを当時の野田首相に進言したが理解できなかったのか聞き入れられなかったそうで、この法曹のプロは「日本の検察は今後50年、信頼回復できない」と断言する。
政治権力や社会悪に真正面から立ち向かうべき検察が自浄機能を失い、体面の維持を最優先して厳正さと真の正義を放棄したとき、社会正義を説く資格はあるのか、捜査に国民の理解が得られるのか。巻末に本書が“ごまかし、詭弁だらけ”と表現する「最高検報告書」「田代報告書」が掲載されているが、過去の裁判で検察側の主張がほとんど採用されてきたことを考えると、いったいどんな証拠改ざんが、調書捏造がなされてきたのか、そしてどんな判決がなされたのか、大いに興味が湧いてくる。
大阪郵便不正事件最大の被害者だった村木厚子氏は、このほど厚生労働省事務次官に抜擢された。この人事に意図はないだろうが、検察はじめ関係者たちはもって瞑すべしだろうし、検察改革は待ったなし、まさに“いつやるか、今でしょう”である。ついでにいえば、検察批判に国策捜査で報復するような見苦しい姿だけは見せてほしくない。
(本屋学問 2013年6月16日)
日本でいちばん小さな出版社/佃由美子(晶文社 2007年 本体1,600円)
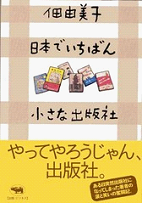 ある日ふと本書が目にとまり題名に引かれて読み始めた。何故引かれたかというと、本会の本屋学問さんがやっているオフィスHANSが一番小さいと思っていたからだ。読んでみると、「なるほど世間には一人二人のマイクロ出版社が多くあるらしい」ということを知った。
ある日ふと本書が目にとまり題名に引かれて読み始めた。何故引かれたかというと、本会の本屋学問さんがやっているオフィスHANSが一番小さいと思っていたからだ。読んでみると、「なるほど世間には一人二人のマイクロ出版社が多くあるらしい」ということを知った。
著者の会社は、気の合う友人と二人で始めた資本金3千万円の株式会社。当初出版とは関係ない事業目的で設立したのだが、ある日突然知人から自著の出版を強引に依頼され、全くの素人なのに、出版の世界に入り込むことになった。これまでかなり多くの本を世に出し、トーハン、日販のような大手出版取次会社に口座を持つようになった今でも、出版業務は自分ひとりで担当している。これならば「日本で一番・・」という資格はあろうか。
この本は素人の著者が見知らぬ業界で知識・経験を積み、成長していく苦労話であり、読み進むにつれ、まるで著者と一緒に未知の世界に分け入るような気分になる。たとえば、「原稿を本の形にするにはどうするのか?」、「それを何処で印刷するのか?」、「本を売るには何処に持ち込むのか?」、これらすべてが新しい課題である。納品を終えて喜んだのも束の間、数ヵ月後に大量の返本処理に追われることになった。数々の困難に遭遇しながらそれらを乗り越え、次第にこの道のベテランに育っていく過程は読みながら興奮を覚える。
本書を読んで学んだのは、出版業界における出版取次会社の比重の重さである。取次とは、出版社と書店の間をつなぐ流通業者であるが、単なる運送業ではなく、書籍の集荷・分散、返品処理、在庫管理、代金回収、金融から需給調節まで、取次が担っている機能は多岐に渡る。したがってトーハン、日販などの大手取次会社に口座を持つのは、出版社にとってステータスなのだ。著者はこれら大手に口座を得た後、逆に小規模な取次会社に「うちは大手に口座を持つような出版社と取引しない」と拒絶されて驚く! 出版・流通業界の裏舞台を覗かせてもらったのは、本好きの一人として興味深い。
感心するのは、本書を一貫して流れる著者の前向きな姿勢である。いろいろ困難に遭ってもへこたれず、自分の能力を開発して解決して行くのは小気味よい。不思議なことに解決困難な問題にぶつかる度に、助けてくれる人と偶然出会ったり、突然状況が好転したりする。「能力開発できる著者の才能は特別」という感じもするが、自分の体験を顧みても、世の中にはこういう小さな奇跡が数多く起こっている。努力する人間には神様が助けを与えているのであろう。正に「天は自ら助くる者を助く」である。新しいことにチャレンジする勇気を与える本として推薦する。
と書き終えた翌日、朝日新聞朝刊に「出版流通、再編幕開け アマゾンの脅威、楽天とタッグも」の見出し! 既存の出版取次業界はAmazonの攻勢に防戦一方だそうだ。業界3位の大阪屋は楽天と組んで生き残りを図る由。20世紀後半の出版・流通業界を支配した体制も21世紀のNET社会で崩壊するのか。強大な出版取次会社もいずれ歴史の一齣になるのであろう。
(狸吉2013年6月17日)