バイエルの謎/安田 寛(音楽の友社 2012年5月 2400円)
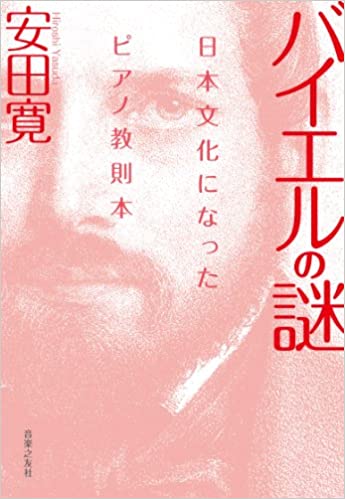
バイエルという名前で呼ばれているピアノ教則本は、明治初期の日本の音楽好きの家庭ではよく知られていて、私も幼児期からこの本のことをよく覚えていたが、最近このバイエルに関する本が出回って来たので思わず買ってしまった。読み進むうち、意外にも原作者のバイエルが曲の選び方並べ方等について、欧米の音楽評論家からかなり厳しい批判を受けてきたが、著者の安田氏は詳しく其の事情を調査したものであることが分かった。同時に、日本ではこの教則本は素直に受け入れられ、今でも高い評価を続けている。
1 バイエル教則本の歴史と現状
バイエルピアノ教則本を作ったのは、ドイツ人フェルデナント・バイエルというピアノ作曲家演奏家で1803年に生まれ、1863年亡くなるまでに多くの練習曲を含む作品を発表したが、このバイエル教則本が日本に持ち込まれたのは1880年頃であった。そして、各国にピアノ練習曲として用いられ、急速に普及していった。
其の主な理由は、演奏曲が容易で入門しやすいこと、母親または教師と連弾できる構成になっていること等であったが、其の特徴が生かされてこのバイエル教則本の普及は目覚しく、多くの子女に愛好され、日本では明治から平成にまでバイエルの人気は衰えなかった。しかし、1900年代になってから、余りにも急なバイエルの人気に疑問を持つ専門家が批判を始めた。余りにも多くの作品が似寄りの内容であるとか、練習用作品にしては鍵盤の1/3以下しか使っていないとか、まるでいじめに近い批判が相次いだため、次第に欧米からバイエルの名前は聞かれなくなった。
本書の著者である安田寛氏は、多くの文献を調査し出来るだけ公平意見を取り上げる努力をされているようであるが、色んな音楽家、評論家の意見は賛否両論に分れ、いまだに議論が尽きない。他方、戦後ピアノの普及が目覚しく、日本ではバイエルの爆発的人気が起こっていた。これは、家庭の母と子のピアノによる結びつきが、如何に音楽教育に重要であるかを示していといえよう。
2 バイエルと音楽教育(バイエルについての個人の感想)
私が小学校1年生のころ、私の母は多少時間に余裕が出来たのか、オルガンやピアノを好きなように弾いて楽しんでいた。母のそばで聞いていた私に、バイエルの1番から引いて聞かせたのが始まりで音楽に興味を持ち始めた。小学校では漢字を習い始め、字が書けるようになっていたが、音はどうやって表現するか知らなかった。そのうちに次第に和音の世界で其の美しさと楽しさに魅了され、同時にバイエルの独習を始めたのである。
中学に入るころにはバイエル100番前後まで何となくこなせるようになったが、チェルニーまでは進めなかった。中学生時代はクラシック音楽に夢中になり、兄のレコードを借りて聞いて楽しんでいた。更に進んで「これで音楽の大綱が分かった。どうしても新しい和音とメロデーを創出したい!」と思い込み、父親に音楽家になりたいので文科系に進みたい」と申し出る積りでいた。しかし、父は多忙で九州出張となり、この話しは立ち消えになった。あれから70年!もし私の音楽部門転出が実現していたら、今頃は無一文になりガード下で野宿するようになっていたかもしれない。しかし、バイエル教則本は私の心に強く残っている。
非球面レンズに挑む!歴史を変えたパナソニックの技術者たち/パナソニック・スーパーレンズ研究会著・中島昌也・長岡良富編(日刊工業新聞社 本体2,400円 2012年2月28日初版発行)

中島昌也/大阪大学大学院通信工学修了。1959年松下電器産業(現パナソニック)入社。無線研究所長、取締役技術本部長、兼松下技研社長などを経て、1995年客員に就任し現在に至る
長岡良富/大阪大学通信工学科卒業。1964年松下電器産業(現パナソニック)入社、1980年工学博士(阪大) 映像研究所長 AV研究所長、取締役などを経てAVC社副社長、監査役。2004年客員に就任。2005年㈱けいはんな 新産業創出・交流センター長、2009年同顧問就任、現在に至る。
パナソニック・スーパーレンズ研究会
1979年松下電器無線研究所内で発足し、全社にまで拡大した開発・事業化PJT。この会は、当時のメンバーが2008年に集結したグループで、主にパナソニック社の定年退職者やこの事業に協力した光学・ガラス業界の関係者約30名で構成。
はじめに
第1章 非球面レンズの生い立ち
第2章 エレクトロニクスメーカーの挑戦
第3章 入念な下準備
第4章 プロジェクションテレビ用プラスチック非球面レンズへの挑戦
第5章 最初のレンズ成型工場設立と実用化
第6章 非球面の計測はどうする
第7章 プラスチックからガラスへ
第8章 ビデオカメラに非球面レンズを
第9章 拡がるレーザー光の応用と非球面レンズ
第10章 デジカメの出現と非球面レンズの定着
あとがき
はじめに:戦後、ドイツを凌いで性能・品質の高さを認められた日本のレンズは、十数年前から高性能非球面レンズの生産が軌道に乗ったことで更にその厚みを増した。このレンズは、光学系の企業ではなく家電メーカーが口火を切って成功させた。十指に余る新技術の壁に挑み、プラスチックから始めてガラスのレンズまで、その実現に至る20年に亘る歴史。
第1章:レンズ改革は光学専門メーカーでなく、素人集団が取り組んだ。プラスチックでバケツや食器を作る感覚で!苦闘の中でもがくうち、KODAKのディスクカメラでは非球面レンズをガラス成形したものらしいと分かり微かな希望が生まれる(82年)。CDプレーヤー用に初めての非球面ガラスレンズが実用化された(86年)。
第2章:ビデオカメラのコストの30%はレンズだった。初めはプラスチックで、プロジェクションTV向けを開発。何とか成功し売れた。
第3章:小倉磐夫(東大生産研究所教授)や中川治平氏(元オリンパス)らの厳しい指導で勉強。「拭き3年、磨き10年」を知る。
第4章: 予算・型作り・成形プロセス・成形機の開発で失敗したら?と聞かれ「金型を抱いて大阪湾へ飛び込む」との発言で認可。
第5章: 超精密成型法の発明(成形時の樹脂収縮を見込んだ圧縮工程の追加など)。PJTnTVに売れたが市場が終焉。
第6章: 独自技術(Computer Generated Hologram法+新アルゴリズム)・超精密測定機も開発して非球面の評価(0.01μm)が実用化。
第7章:プラスチックでは温度や湿度の影響を受け限界。ガラスに挑戦。決め手は材料。常識破りの超硬合金+白金膜使用の「半永久寿命金型」の発明。ガラスではプラスチックの数十倍高い精度のレンズが出来た。量産化には苦労。クリーンルームで。BD用のピックアップには今でもプラスチック非球面レンズが多いが、映像用のレンズは逆でガラス製が全盛。
第8章:前玉からインナーフォーカシングへ。同性能を小形軽量に実現。「他社のマネをしないS社がこれを真似た」と業界誌。外販も。
第9章:光通信用非球面レンズへの展開。
第10章:あらゆる優れた要素技術を持つことを知った中村邦夫は、デジカメへの再参入を号令。LUMIXが生まれた。レンズの販売額は600億円/年(山形工場)。LUMIXのレンズには「LEICA」のロゴがあるがライカ製ではなく、あの気位の高い同社が認めた品質保証で生産されたレンズに付与されるブランド名なのである、と初めて知った。それだけパナソニックのレンズが優れているということなのであろう。
あとがき:
書感: 私の知人も2人登場する、と共通の友人からこの著作の存在を知らされた。レンズや光学の専門家であるが、まさかこのプロジェクトに参画していたとはつゆ知らずに来た。雑談の中で、非球面レンズの話に及んだ場合でも彼らはPJTへの参画の話は一切触れていなかったので。ガラスの、それも非球面レンズをモールドで成形する、という非常識をどうやって実現したか知りたくて一気に読了した。「非球面は作り難く使えない」という技術の壁は20世紀末をもって崩れた。この著書はその開発や事業化に挑戦したあくなき技術者魂の記録。ブレークスルーへの信念・情熱の記録とも言える。淡々と記述されているが、それ以上に大きな苦労があったことは容易に想像できる。新規開発PJTに参画する研究者・技術者にお奨めの一書である。
(恵比寿っさん 2012年9月6日)
国富消尽―対米隷従の果てに/吉川元忠・関岡英之(PHP研究所 2006年 本体1,500円)
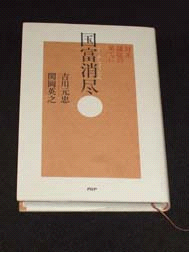 日本のバブルと崩壊後の長い不況の原因は、実はアメリカの経済圧力に屈した政府と通貨当局にあると論じる、興味深い警世の書である。吉川は「マネー敗戦」、関岡は「拒否できない日本」で、大手マスコミがあまり取り上げなかった日本経済失速の真相をすでに世に問うているが、本書では対談の形で改めてアメリカによる日本解体計画の全貌を描いている。
日本のバブルと崩壊後の長い不況の原因は、実はアメリカの経済圧力に屈した政府と通貨当局にあると論じる、興味深い警世の書である。吉川は「マネー敗戦」、関岡は「拒否できない日本」で、大手マスコミがあまり取り上げなかった日本経済失速の真相をすでに世に問うているが、本書では対談の形で改めてアメリカによる日本解体計画の全貌を描いている。
「国を挙げて外資によるM&Aを後押し」、「アメリカのエージェントと化した日本の新聞」、「三角合併を推進した日本経団連の愚」、「英米法は遅れた法体系」、「日銀が意図的につくりだしたバブル」…と挑戦的なテーマが並ぶが、二人とも大手銀行で長く産業調査や証券投資業務に携わり、ドルを支え、ドルの罠に落ちた日本経済の20年をつぶさに見てきた当事者だけに、説得性十分な論理を展開している。
イギリスは、貿易と海外投資によってポンドを基軸通貨として世界に循環させ、発展途上国の資金需要を担い、最大の債権国として世界最初の「帝国循環」を実現した。しかし、イギリスに代わって覇者となったアメリカのドルは、彼らの過剰消費型経済のためか長続きせず、1980年代のレーガン政権下で経常(貿易)収支と財政収支の赤字、いわゆる“双子の赤字”を生み、その後アメリカは赤字補填に海外からの投資を求めた。対外純資産の貯金を使い果たして以後は、経常収支の資金流入は純債務となって増え続け、世界最大の債務国に転落する。「プラザ合意」で苦肉のドル安誘導をはかったのもこの時代だった。
そこで、アメリカへの資金導入の中心的役割を果たしたのが巨額の貿易黒字を抱えていた日本で、やはり黒字国だったドイツは賢明にも忌避したが、当時の大蔵省は日本の生命保険会社を行政指導して巨額のアメリカ国債を買わせ、アメリカを支えた。日本はたちまち世界最大の債権国に躍り出るが、アメリカは赤字を上回る資金を日本などから調達し、余剰分を海外に還流させるという奇妙な「帝国循環」の構図をつくり出した。吉川はこれを、日銀が刷ったマネーが循環してアメリカのウォール街を潤し、その一部が日本に還流して日本を買いまくる「新帝国循環」と表現している。
アメリカが日本市場の閉鎖性を訴え、行政、経済構造改革を迫った「日米構造協議」とは、実は数千兆円といわれる日本の国富をアメリカが吸い上げるための周到な日本改造計画にすぎなかった。アメリカが相手国に何かを要求するときの常套手段が「トロイの木馬」作戦だという。つまり、日本国内でアメリカと利害が一致する著名人や団体に全面的に力を貸し、アメリカの要求を“日本の必要”として代弁させる。そういう勢力を「ドメスティック・アライズ」(国内の同盟者)と呼ぶそうで、“消費者のため”という論理とトロイの木馬戦略に振り回され完全にアメリカの罠にはまったのが、この20年の“失われた日本”の本質だと本書はいっている。
注目すべきは、従来の中心的債権国だったイギリスやアメリカは、自国通貨であるポンドやドルで資本輸出をしたが、日本政府と大蔵省は円でなくドル建て、つまり、債務国の通貨建てという、ビジネスルール上前例のない決済方法によったことだ。実はここに、世界最大の債権国が経済危機に陥り、債務国が好景気になるという1990年以降の異常現象があると本書は指摘する。
ドルは事実上の機軸通貨でありながら、アメリカ一国の意向でその価値を自由に変動できるという、国際通貨システムの根幹にかかわる危険性にあえて目をつぶった当時の日本政府や大蔵省、日銀などの責任は重大で、同時にドルを支える以外に独自のマネー戦略を持たなかったことが、日本にとって最大の悲劇であるとも論断している。同じことは、防衛、外交、貿易政策にもいえるのかもしれない。あるシンクタンクの試算では、先の円とドルの為替差損だけで30兆円、バブル崩壊後の株の時価総額損失420兆円、土地評価額損失380兆円が日本から消えたそうだ。日本が丸裸になったとき、アメリカが狙う次の標的は中国なのか。
郵政民営化は、国が保険業務にかかわるのは良くない、郵政公社は4分割せよというアメリカの要求が、「構造改革」「規制緩和」という日本国民の耳に心地良い響きとマスコミの情報操作が重なって、郵便貯金・簡易保険の350兆円が外資の好餌になった。日本の財政赤字を増やしてアメリカの赤字を埋める異常な構造。日本が持つアメリカ国債こそが、日本の究極的な不良債権だという。
海外の保険業界にとって日本市場は魅力的で、とくに医療、疾病、傷害保険は、従来から外資系保険がニッチとして新規開拓、参入した分野であるが、いざ規制緩和する段になり、日本国内の大手保険が参入すると既得権益が脅かされる外資系が最も反対したというブラックジョークも生まれた。保険業法改正で日本の中堅・中小生命保険会社はほとんど破綻し、外資系が取って代わった。アメリカの大型店進出のために「大規模小売店舗法](旧大店法)を廃止した結果、日本の小売店が大打撃を受け、いわゆる“シャッター街”が全国に出現したのと同じ構図である。古くは日本の小麦農業の消滅があり、新しくはTPPの脅威かもしれない。
あまりにも個人主義に偏ったアメリカ型システムは現在、日本の企業経営をはじめ医療システム、教育制度まで及びつつある。この惨状から立ち直るには、アメリカへの過度な依存を是正し、アングロ・サクソン的価値観から決別して、日本の終身雇用や年功序列といった集団主義的価値観など、先人たちが築き上げてきた歴史と伝統の良さを再認識し、私たちが再び自信と誇りを取り戻す以外にないと本書は説いている。
戦前の日本には、欧米に迎合せず、ロシアや中国に阿ることもなく、全世界、全アジアを視野に入れた世界観を持った人々がいた。これから新しい体系的国家戦略を確立するには、日本の知的インフラを強化し、アメリカに対抗できる新しい思想体系を構築して、たとえば満鉄調査部のような強力なシンクタンクの創設が国策上必要だと本書はいう。アジア、イスラム中心のポスト・グローバリズムの実現に軸足を移し、1000年続く日本の優秀な官僚制度を効果的に生かして、再び日本らしい求心力を創造することだという。
小学校から英語教育を、社内会議は英語でという発想は否定しないが、日本人はそもそもアングロ・サクソン流の弱肉強食の生きかたには馴染まない。アリとキリギリスの寓話ではないが、キリギリスの夏の生活もアリが支えているのは明らかにおかしいという。今こそ日本は、新しい世界観に立脚した新しい思想を持つべきだと結んでいるが、一般紙や経済紙が伝えない日米経済の本質がわかって面白い。
(本屋学問 2012年9月5日)
「長生き」が地球を滅ぼす/本川達雄(文芸社文庫 2012年8月)
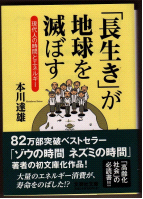
著者は生物学者で、以前「ゾウの時間、ネズミの時間」という本の著者で、70年生きるゾウも1年で死ぬネズミも、心臓の打つ回数はどちらも15億回と同じであるということから、エネルギーと生きる時間を関連付けて考えて来られています。
動物の心臓の時間(寿命)は、大きくても小さくても、体重の1/4乗に比例しており、人間は縄文時代30年の寿命と推定されているが、それが戦後50才になり、現在80才年の長寿になっている。
長寿になったのは、医療の進歩、衛生の改善、豊富な食料、冷暖房のお陰という現代文明の莫大なエネルギーを使ってつくりだした人工的な寿命である。
時間の速度がエネルギー消費量に比例するため、社会生活の時間もエネルギー消費量に比例する。
食べて体が使うエネルギーは他の動物並みだが、現代人は石油や石炭から得たエネルギーを大量に使っている。著者の計算では、体が使う分のエネルギーに対して、明治初期で2倍程度、昭和30年以降になると10倍になり、現在に至っては30倍以上のエネルギーを使っている。
その結果、便利になって時間の速度が速くなり、日本国民の半数近くが社会生活のテンポが速すぎていると感じている。
体の時間は昔と変わらない。もっと適切な時間環境があるはずで、無意識に時間環境を破壊している。老人は社会の進みに追いつきにくくなる。皆、ストレスが生じ、親も不満、子も不満という高齢化社会になってしまった。
高齢者医療に莫大なエネルギーを投入、エネルギーの大量使用による環境汚染、核廃棄物は世代を越えて後世の重荷になる。
前世代から受け継いだ自然界の資産、自然界の持つエネルギーを無用に使い過ぎて、次世代に回すことが出来なくなっている。輪廻転生の概念を思い起こすよう訴えている。
時間の速度がエネルギー消費量(仕事量)に比例すると考えると、ただ病院のベッドに横たわっているだけの時間など、あって無きがごときものと見なせる。老人といえども働いてこそ幸せになる。寝たきりの長寿は幸せではない。
便利になりすぎがストレスを生んでいる。今の生活を振り返って、安易に便利さには飛びつかず、昔のようにゆったりした生活環境に戻せるものは戻すべきと本書により再認識した次第です。
その基はホツマツタヱ13綾の中の「スズカの道」という私欲を取り除いて清く正しく美しく生きることの教えに結びつくことを知りました。私欲を出しては魂の緒が乱れ末代まで続きません。とあり、見直しの原点であるような気がしました。
(ジョンレノ・ホツマ 2012年9月16日)
人間の基本/曽野綾(新潮社 定価680円)
 著者の曽野綾子さんと言えば、右翼と言って嫌うひともいますが、そう言う人に読ませたいのが本書である。著者は、人間のあるべき姿を正直に表現している。扱うテーマは、世間体的に言うと、言いにくい事が多いのだが、著者自身が生活体験として実践しているので説得力がある。著者を嫌う人はそれなりに耳の痛い人達と思う。
著者の曽野綾子さんと言えば、右翼と言って嫌うひともいますが、そう言う人に読ませたいのが本書である。著者は、人間のあるべき姿を正直に表現している。扱うテーマは、世間体的に言うと、言いにくい事が多いのだが、著者自身が生活体験として実践しているので説得力がある。著者を嫌う人はそれなりに耳の痛い人達と思う。
そう言う、曽野綾子さんのエッセイ集が本書である。全体が8章から構成され、第1章が「人間本来の想像力とは」、第2章が「乗り越えるちから」、第3章が「ルールより人としての常識」、第4章が「すべてのことに両面がある」、第5章が「プロの仕事は道楽と酔狂」、第6章が「ほんとうの教養」、第7章が「老・病・死を見すえる」、第8章が「人間の基本に立ち返る」と言うテーマを挙げている。
全ての章が痛快であり、同時に成るほどと考えさせられる面が有って、面白く一気に読破してしまった。ここで全て語ることは出来ないので、本書の特徴となる部分を私なりの感性に従って紹介したい。
「第1章の人間の想像力とは」から引用してみる。『私がよく「東大法学部は駄目」と言うのは、高度成長期に作られた、有名大学から一流企業に入れば一生安泰、と言う錯覚がどうしようもなく刷り込まれているからでしょうね。人は学歴だけでは生きて行けない、試験の成績と本質的な生活能力とは違う、それを認めようとしない。頭でっかちで人間にとって根本的な部分を欠いた人間は、社会にとってむしろ毒害となります。』と言うくだり痛快ですね。
第1章にはこんなのもありました。『生活保護者の受給者の中には、体はいたって健康なのに、お金を受け取った足でタクシーに乗って競輪場へ行くようなひとがいます。働きたいのに働けない、というやむを得ない事情を持つ人と、単なる怠惰な人とを同じ様に保護する必要はないと思います。ましてや賭け事などしたら即座に打ち切ってかまわないと思います。』
「第7章 老・病・死を見すえる」からの引用です。『私は年をとって何も楽しみがなくなった、と言う話を聞くと不思議で仕方ありません。男性なら料理教室に出かけてちょっと綺麗な中年の奥さんとお友達になって、たまにはお茶を飲むぐらいしてもかまわない。その程度のやましさはちょうどいい』と言うくだり、頂きですね。
こんなのもあります。『三食付の老人クラブみたいな刑務所に多額の税金を投入するくらいなら、尖閣諸島に移して住んでもらいたい』と言うものがある。実はこの案、最近公務員に住まわせると言うのが、政府要人から出てきており、良い事は何でもいい。それなら、世の中に害を及ぼす東大卒を住まわせればと思うのである。
と言う具合で実に痛快かつ面白いという事で、書き出すときりがないので、是非読書をお勧めしたい。
著者に因んで、私も一言。原発反対のデモに子連れで参加しているのをみるにつけ、選挙の投票率が極めて低いのに何故ここまでやるか、と思うのである。選挙による民意の達成が先と思うが。
今の為政者とて基本は原発反対と言っている、たぶん本心であろう。デモに参加する人達に、今原発をやめて、そこから派生する全ての非文化生活を受ける覚悟があるのか、将来に及ぼす国力の低下を容認出来る覚悟があるのかを問いたい。
(致智望 2012年8月5日)